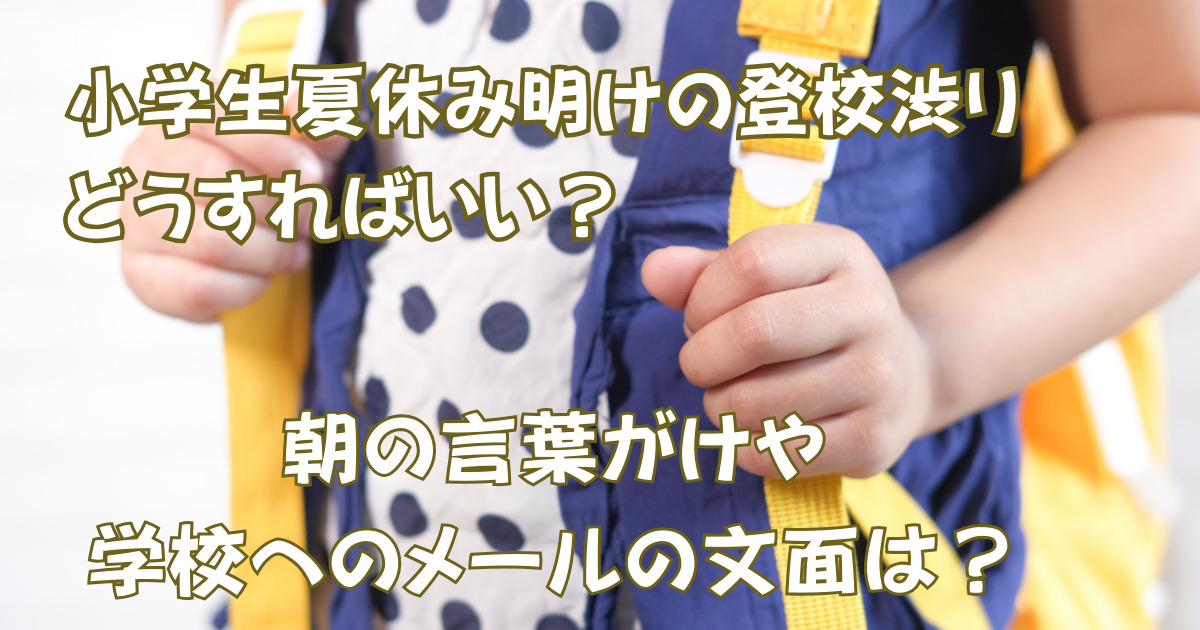いよいよ2学期が始まる夏休み明け!
友達との交流を楽しみにしている小学生の子どもたちも多い中、登校を渋りがちになる場合も増えているようです。
夏休みという家族とほっとできる時間を過ごせていた子どもにとって、学校という集団生活へ戻ることは大きな抵抗を感じる場合もあるのでしょう。
実際に文部科学省の調査によれば、長期の休み明けに登校できなくなる子どもは全体の約4割に上るという結果が報告されています。
親にとって夏休み明けの登校渋りは、その後の長期的な不登校への兆しではないかと不安でいっぱいですね。
夏休み明けは子どもにとって大きな転機であり、心理的・身体的な不調を引き起こす可能性が高いことを意味していると言えるでしょう。
今回は、小学生の夏休み明けの登校渋りについて、「どんな対応をすればよいか?」「朝の声掛けはどんな声掛けがいいのか?」さらに担任の先生へのメールの文面などを具体的に解説していきます。
お子さんが登校を渋ったら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
夏休み明けにおける登校渋りの原因

夏休み期間中、子どもたちは家庭で安心して過ごすことができるため、「家の方が安心」という感覚が強まります。
また、生活リズムが乱れがちになり、朝の起床時間や食事のタイミングもルーズになっている場合が多いですね。
そんな夏休みを過ごした子供たちにとって以下のことが、登校渋りの要因としてあげられます。
- 生活リズムの変化
夏休み中に夜更かしや昼夜逆転の生活になりがちで、規則正しい生活に戻ることが苦しい。 - 安心できる居場所の喪失
家庭は子どもにとって安心感の源ですが、学校は友人関係、教師との相性など様々なストレス要因が存在する。 - 学習面および社会的なプレッシャー
高学年になるにつれ、学業のプレッシャーや友人関係の変化、いじめなどによって登校への不安が大きくなる事例が多くみられる。 - 心理的な抵抗感
休暇中に経験したリラックスした環境と、学校で求められる規律や集団生活とのギャップが、心理的負担となり「行きたくない」という感情を引き起こす。
これらの要因は、夏休みなど長期休業中明けの登校渋りを引き起こしていることが多いことは事実です。
ですから、家庭が居心地が良い場所であるとも言えますね。
居心地の良い家庭であることは、親子の関係も良好なため、子どもが「学校へ行きたくない」という自分の気持ちを素直に言うことができるとも言えるでしょう。
まずは、子どもの気持ちを受け止めてあげることが重要です。
各学年ごとの登校渋りの特徴と対応策

夏休み明けの登校渋りは、学年が進むにつれて現れる原因やその背景が変化していきます。
各学年ごとの特徴と、対応すべきポイントを整理しました。
低学年の場合
低学年の子どもは、分離不安が強く、家庭という安心できる環境から離れることへの抵抗感があります。
また、まだ自己表現が未熟で、具体的な不安の理由をうまく言葉に出すことができない場合が多いと言えます。
対応策
- 家庭内で安心感を強化する
- 体調不良や不安を訴えた場合は、子どもの気持ちを否定せずに共感する
- 朝のルーティンをシンプルにし、負担をかけないようにする
中学年の場合
中学年の子どもは、低学年に比べて少し自己主張が始まりますが、まだまだ感情表現が十分に発達していないため、理由を明確に言語化することが難しいと言えます。
環境の変化や新しい教師との関係、休暇明けのルーティンへの不適応が顕著です。
対応策
- [今日はどうしたい?]と選択肢を与える声かけを行う
- 無理に理由を聞き出さず、子どもがリラックスできる環境を提供する
- 学校の新しい環境への不安を和らげるコミュニケーションを工夫する
高学年の場合
高学年になると、子どもは学業面でのプレッシャーや友人関係、時にはいじめといった具体的な問題を抱えるケースが増えます。
登校渋りの理由を具体的に説明できる場合も多いですが、その分自己批判や過度な責任感に悩むこともあります。
対応策
- 子どもの言葉に耳を傾け、否定せずに受け入れる
- 学業や友人関係での悩みを共有し、改善策を一緒に考える
- 学校側との連携を強化し、適切なサポート体制を構築する
保護者が実践できる10の具体的対応策

登校を渋るわが子にどのような対応をすればよいのか迷いますよね。
この項目では、保護者が実践できる具体的な10の対応策を示します。
それぞれの項目は、全学年に共通するものと、学年別に調整すべきポイントを含んでいます。
1. 気持ちを受け止め共感する
「行きたくない」と感じる子どもの気持ちを否定してはいけません。
「今日はそのように感じるのは仕方ないよね」と温かく受け止めることが重要。
学校へ行きたくないという気持ちを共感することで、子どもは自分の気持ちを分かってもらえたという安心感を得やすくなります。
2. 無理に行かせず、選択肢を与える
「今日はどこまでなら行けそう?」というように、無理なく選択肢を提示すのもよいでしょう。
子ども自身が自分でペースを決められるようにすることで、強制されているという感じを受けずに、自己決定感を尊重する姿勢を示すことができます。
3. 規則正しい生活リズムを整える
夏休み中に乱れがちな生活リズムを見直し、決まった時間に起床、朝食、準備する習慣をつけることが、学校生活への円滑な再適応につながります。
生活リズムを具体的に示して、一緒に朝のルーティーンを進めてみましょう。
[表:朝のルーティン例]
| 項目 | 具体例 | 説明 |
|---|---|---|
| 起床 | 7:00~7:30 | 規則正しい起床時間で体内時計を整える |
| 朝食 | 7:30~8:00 | 栄養バランスの取れた朝食でエネルギー補給 |
| 身支度 | 8:00~8:15 | 学校に向けた身支度をゆったりと済ませる |
| 出発準備 | 8:15~8:30 | 余裕を持った出発で精神的にもリラックスできる |
この表は、あくまでも規則正しい朝のルーティンを整える一例です。
それぞれのお子さんに合ったペースに合わせ、柔軟に対応してください。
4. 理由を無理に聞き出さない
中学年の子どもは、具体的な理由を上手に表現できない場合が多いため、「なぜ行きたくないの?」と責めるのではなく、「今日は何か不安なことがあった?」と柔らかく聞いてみましょう。
登校渋りがとても強い場合は、まずは共感することに徹して、理由を無理に聞くことはやめましょう。
5. 家庭内で安心できる居場所を作る
低学年の子どもは、家庭が安心の場であるため、学習や遊びのスペースとして家庭内に「安心コーナー」を設けることも有効です。
「安心コーナー」には、子どもがリラックスできるアイテムやおもちゃ、ゲームなどをそろえておくと良いでしょう。
心の安心が登校へのエネルギーになります。
6. 学校及び担任教師との連携を強化する
登校渋りが継続する場合、家庭だけでなく学校にも状況を共有し、担任やスクールカウンセラーと協力してサポート体制を作ることが必要です。
特に6年生は進路も控えています。
状況を客観的に伝え、学校への協力をお願いする姿勢が大切です。
7. 子どもの自己表現を尊重する
高学年の子どもは登校渋りの理由を具体的に語れる場合が多いため、子どもの言葉にしっかりと耳を傾けましょう。
子どもが自分で心を開いた場合は、決して否定してはいけません。
「今はこう感じるんだね」と、子どもの思いや感情をまずは受け止めましょう。
その上で、共に解決策を話し合うことが重要です。
8. 小さな成功体験を積むためにポジティブなフィードバックを与える
登校渋りや不登校の子どもの中には、自己肯定感が低くなっていることが多いです。
朝の登校や学校内での小さな進歩をみつけ、「すごい」「よく頑張ってるね!」などの声がけをしましょう。
子どもの自己肯定感を育むことが、問題解決への最も早い近道です。
積み重ねた成功体験が、登校に対する不安を和らげ、自信を取り戻す手助けになります。
9. 学校生活の楽しみ・期待を一緒に見つける
夏休み明けの緊張感を和らげるために、「2学期の学校で楽しみにしていることは何?」など、子ども自身が学校に対して前向きな興味を持てるように声掛けをしましょう。
一日の学校生活の中で、ほんの少し楽しいことが見つかれば、登校に前向きになるきっかけになります。
たとえば、学校のイベントや好きな授業、学校での好きな遊びや好きな場所などを具体的に語り合えるといいですね。
10. 状況が改善しない場合は専門家に相談する
もし上記の対応策を実施しても状況がなかなか改善しない、または登校渋りの状態が長期間続く場合は、スクールカウンセラーや心理士、医療機関など専門の助言を求めることをお勧めします。
専門家を通して、的確な対応を積み重ねることで、必ず良い方向に向かうことができます。
保護者が実践できる10の具体的対応策

夏休み明けの登校渋りに対して保護者が実践できる具体的な10の対応策を示します。
それぞれの項目は、全学年に共通するものと、学年別に調整すべきポイントを含んでいます。
お子さんの状況を考えながら、対応を検討してください。
1. 気持ちを受け止め共感する
まず「行きたくない」と感じる子どもの気持ちを否定せず、「今は学校へ行きたくないんだね」「〇〇が嫌で悩んでいるんだね」など温かく受け止めることが重要です。
思いに共感することで子どもは安心感を得やすくなります。
2. 無理に行かせず、選択肢を与える
無理やり学校へ行かせることはやめましょう。
「今日はどこまでなら行けそう?」というように、無理なく選択肢を提示し、子ども自身がペースを決められるようにするのもよい方法です。
自分で選ぶことで、親から強制されているという気持ちを軽減し、子ども自身が自己決定できたという思いを持つことができます。
3. 規則正しい生活リズムを整える
学校へ行かない場合も、生活リズムを整え、決まった時間に起床、朝食、準備する習慣をつけることが、学校生活への円滑な再適応につながります。
[表:朝のルーティン例]
| 項目 | 具体例 | 説明 |
|---|---|---|
| 起床 | 7:00~7:30 | 規則正しい起床時間で体内時計を整える |
| 朝食 | 7:30~8:00 | 栄養バランスの取れた朝食でエネルギー補給 |
| 身支度 | 8:00~8:15 | 学校に向けた身支度をゆったりと済ませる |
| 出発準備 | 8:15~8:30 | 余裕を持った出発で精神的にもリラックスできる |
この表は、規則正しい朝のルーティンを整える一例です。子どもに合ったペースに合わせ、柔軟に対応してください。
4. 理由を無理に聞き出さない
中学年の子どもは、具体的な理由を上手に表現できない場合が多いため、「なぜ行きたくないの?」などと責めるのような声掛けはやめましょう。
「何か不安なことがある?」など、柔らかく聞くなどして、様子を見ることが大切です。
5. 家庭内で安心できる居場所を作る
低学年の子どもは、家庭が安心の場であるため、学習や遊びのスペースとして家庭内に「安心コーナー」を設けることも有効です。
子どもがリラックスできるアイテムや思い出の品をそろえておくと良いでしょう。
子どもの心が安定することで、心のエネルギーが高まります。
6. 学校及び担任教師との連携を強化する
登校渋りが継続すると親も心配になりますね。
家庭だけで悩んでいては、親も疲弊してしまいます。
担任の先生やスクールカウンセラーと協力してサポート体制を作ることが重要です。
学校への連絡は、状況を客観的に伝え、ともに協力するようお願いしましょう。
7. 子どもの自己表現を尊重する
高学年の子どもは登校渋りの理由を具体的に語れる場合が多いです。
子どもの言葉にしっかりと耳を傾け、否定せずに「そう思うんだね」と子どもの感情を受け止めてあげましょう。
十分に子どもの思いに寄り添うことで、お互いに解決策を話し合うことができるようになります。
ただし、親が勝手に指示したり子どもの思いを勝手に解釈したり、親の思い通りにしようとしたりするのは逆効果です。
子ども自身が自分で方向性を決めることができるように、待ってあげましょう。
8. 小さな成功体験を積むためにポジティブなフィードバックを与える
朝の登校や学校内での小さな進歩に対し、「よく頑張れたね!」「すごいね」などと声をかけ、子どもの自己肯定感を育むことが重要です。
積み重ねた成功体験が、登校に対する不安を和らげ、自信を取り戻す手助けになります。
9. 学校生活の楽しみ・期待を一緒に見つける
夏休み明けの緊張感を和らげるために、学校で楽しいことを一緒に見つけるのもよいでしょう。
子どもにとって、学校での楽しみは意外なことである場合が多いです。
例えば、給食や好きな場所での遊び、中庭で虫取りができるとか、鉄棒遊びが好きだとか、子ども自身が学校に対して前向きになる場面があれば一緒に共有してあげましょう。
ちょっとでも楽しいことが見つかれば、学校への登校の壁が低くなるはずです。
10. 状況が改善しない場合は専門家に相談する
いろいろな対応策を実施しても状況が改善しない場合もあります。
また登校渋りの状態が長期間続く場合もあるでしょう。
そんな時は、スクールカウンセラーや心理士、医療機関など専門の助言を頼りにすることをお勧めします。
特に長期にわたる不登校となると、親御さんの心のケアもとても重要です。
一人で頑張らないで、様々な人の支援を受けることが、登校渋りや不登校から抜け出す近道になります。
登校渋りをする子どもへの具体的な声がけと学校への対応

登校渋りをする子供たちに実際にどんな言葉がけをすればよいのでしょうか?
迷うところですよね。
今回は、低学年(1〜2年)、中学年(3〜4年)、高学年(5〜6年)に分け、夏休み明けの登校渋りに対する対応を以下の3項目で段階を追ってまとめてみました。
- 【家庭でできる具体的対策】
- 【具体的な声かけ(短いフレーズ)】
- 【学校との連携】
年齢ごとの発達特性に合わせて、実践しやすい方法を挙げていますので参考にしてください。
低学年(1〜2年)
小学校低学年の発達の特徴として挙げられるのが、言語での表現や自己調整が未熟であることです。
ですから安心できる具体的なルーティンや親の身体的・感情的な近さが重要なポイントと言えます。
家庭でできる具体的対策
- 段階的な慣らし:まずは朝まで一緒に過ごす→玄関まで一緒に行く→教室の前まで行って先生に引き渡す等、細かいステップを設定して無理のないように実践してみましょう。
達成ごとにシールやスタンプで見える化するのも子どもが喜ぶ場合はよいと思います。 - 朝の準備を一緒にする:服選び・ランドセルの準備・持ち物チェックを子どもと一緒にやると安心感が増します。
ちょっとしたことができたら必ず褒めましょう。
頭をなでる、ハグするなど体全体でほめてあげると、子どももとても安心します。 - 生活リズムの調整:夏休み後は学校へ行けない場合も、起床時間や就寝時間を決めて守るように支援しましょう。
寝る前のスマホやゲームは時間を区切ったり、一緒に本を読んだりするのもよいでしょう。 - 安心物(お守り)を用意:家で使っている小物(ハンカチ、写真、メモ)をランドセルに入れておくと心の支えになることが多いです。
- ごほうび・可視化:簡単な「行ったらシール」を貼る表を作り、小さなご褒美(週末のおでかけ、好きなおやつ)を設定するのも有効です。
具体的な声かけ(短め・例)
- 「今は不安なんだね。ママ(パパ)と一緒に玄関まで行こうか。」
- 「一緒に持ち物チェックしてから行こう。」「凄い!一人でできたね」
- 「もしつらくなったら先生に声をかけてね。すぐ迎えに行くよ。」
学校との連携
- 担任への連絡内容:家庭での様子(起床時間・不安の言葉)、段階登校希望(玄関→教室前→保健室登校等)、安心物の利用許可。
- 学校にお願いする配慮:登校初日は担任・友達が迎えに来る、保健室で短時間休める、クラスの仲良しを見つけて教室まで一緒に来てもらう等。
- 連絡方法:朝の急な不調は電話連絡、長期的な状況は担任面談やメールで共有。スクールカウンセラーがいる場合は相談を依頼。
中学年(3〜4年)
中学年の発達の特徴として挙げられるのが、「自己表現力が向上し友人関係の影響が大きくなる」ことです。
しかし、理由は話せるようにはなりますが感情のコントロールはまだ不安定な時期でもあります。
家庭でできる具体的対策
- 原因の具体化ワーク:「学校で何が嫌なのか」を一緒に紙に書く(友達・授業・担任・体調など)。紙に書いて視覚化すると対応が取りやすい。
ただし、素直に自分の気持ちを書き出すまでには時間がかかる場合もあります。
簡単に理由がわかる場合は、解決も早いですが、理由を言いたくない場合や適当に理由を言っている場合なども考えられます。
ただし、親子で一緒に考える時間をとること自体が子どもにとっては安心できる時間になるでしょう。
- 段階登校プラン:登校してみようかな?と思えるようになったら、登校のプランを一緒に考えるとよいでしょう。例えば、午前のみ・1限だけ・保健室から教室に入る等。また、親が付き添えば登校できる場合はなるべく付き添ってあげましょう。
- 友人関係の支援:友達との関係が良好だったり、友達が来ることを喜ぶような場合は、クラスの仲の良い子に協力してもらい、遊ぶ時間を確保するのもよいでしょう。
- 塾や習い事には行くことができる場合は、積極的にいかせてあげましょう。
学校とは異なる集団にはスムーズに行ける場合は、「学校に行くことができないのに・・・」などと言わずに、「好きなことできるのとっても嬉しいよ」と喜んであげましょう。
具体的な声かけ(短め・例)
- 「何がつらいか、紙に書いてみない?一緒に考えよう。」
- 「今日は1時間だけ教室に行ってみようか。終わったら一緒に○○しよう。」
- 「友だちの○○くんに会えるかな?会えたら嬉しいね。」
- 「呼吸を3回ゆっくりやってみよう。落ち着いたら教えてね。」
学校との連携
- 担任・学年主任への相談:問題の可能性(特定の友人とのトラブル、授業内容の困難さ)を具体的に伝える。必要なら友人関係の調整を依頼。
- 児童相談・スクールカウンセラーの活用:子どもが自分の言葉で話せない場合、専門家の面談を手配してもらう。
- 段階的復帰の合意:家庭と学校で「いつ・どこまで」登校するかのプランを文書やメールで共有し、担任が受け入れやすいように調整する。
高学年(5〜6年)
高学年の発達の特徴は、論理的思考が進み自己評価が高まる一方、仲間関係や成績への不安が大きくなることです。
自律性を尊重しつつ支援することがさらに求められます。
家庭でできる具体的対策
- 子どもと一緒に目標設定:短期(今週)・中期(1か月)で達成したいことを話し合い、本人が納得する目標を立てる。
- 自己管理の支援:登校チェックリストやタイムスケジュールを一緒に作る。スマホのアラームや通知で起床管理を促す。
- 解決策を一緒にシミュレーション:嫌な場面(授業中の発表・休み時間の居場所など)をどう切り抜けるかロールプレイする。
- 居場所の確保:保健室登校の活用や、学年の相談窓口、信頼できる先生を決めておく。
- 選択権を与える:今日はまず教室に行って廊下で休む/午前だけ行く等、本人に選ばせることで主体性を保つ。
具体的な声かけ(短め・例)
- 「今の気持ちを教えてくれる?一緒に対策を考えよう。」
- 「まず今週は○日だけ学校に行ってみようか。達成できたら週末に選べる楽しみを用意するよ。」
- 「もし授業で困ったら〇〇先生に声をかけていいよ。味方はいるからね。」
- 「どの場面が一番イヤ?それならこうしてみたらどう?」
学校との連携
- 担任・学年主任・進路担当との具体的調整:授業中の配慮(発表を減らす、席の配置)、評価や欠席扱いの相談、テストや宿題の配慮を話し合う。
- カウンセリングや第三者の支援:スクールカウンセラーや校外の心理相談窓口に相談し、必要なら保護者同伴で面談を受ける。
- 情報共有の合意:家庭と学校で定期的(週1回など)に状況報告や目標の見直しをする約束をしておく。書面やメールで合意内容を残すとブレが少ない。
- 将来(進学)への不安が背景にある場合は、担任と連携して学習支援や個別指導の検討をする。
共通して使える「やさしい言葉がけ」
登校渋りや不登校の子供に共通して使える声掛けを紹介します。
- 「話してくれてありがとう。今はつらいね。」
- 「全部じゃなくて、今日はここまでで大丈夫だよ。」
- 「一緒に考えようか。無理はしなくていいよ。」
- 「できたことをちゃんと見ているよ。小さなことでもすごいよ。」
どの年齢の子どもも、「自分の気持ちを分かってくれる。」「支えてくれる。」「味方になってくれる。}という思いを持てる言葉がけは、心の安定を図ることができます。
その他抑えてほしい3つのポイント
- 学校への連絡は具体的に
学校や担任への連絡は「時間帯・症状・希望する支援(保健室登校・段階登校等)」を簡潔に伝えるとスムーズです。 - 変化が長引く場合は専門家を頼る
2〜3週間以上続く、生活リズムが崩れる、食事や睡眠に著しい影響がある場合は専門家(小児科・心療内科・児童心理士)への相談を早めに検討しましょう。 - 親自身のケアも大事
対応に疲れたら周囲(親族・友人・地域の保護者)に相談し、外部支援を得ることが重要です。親自身も悩み苦しい状況に陥ることが多いでしょう。自分自身のメンタルケアもとても大切です。